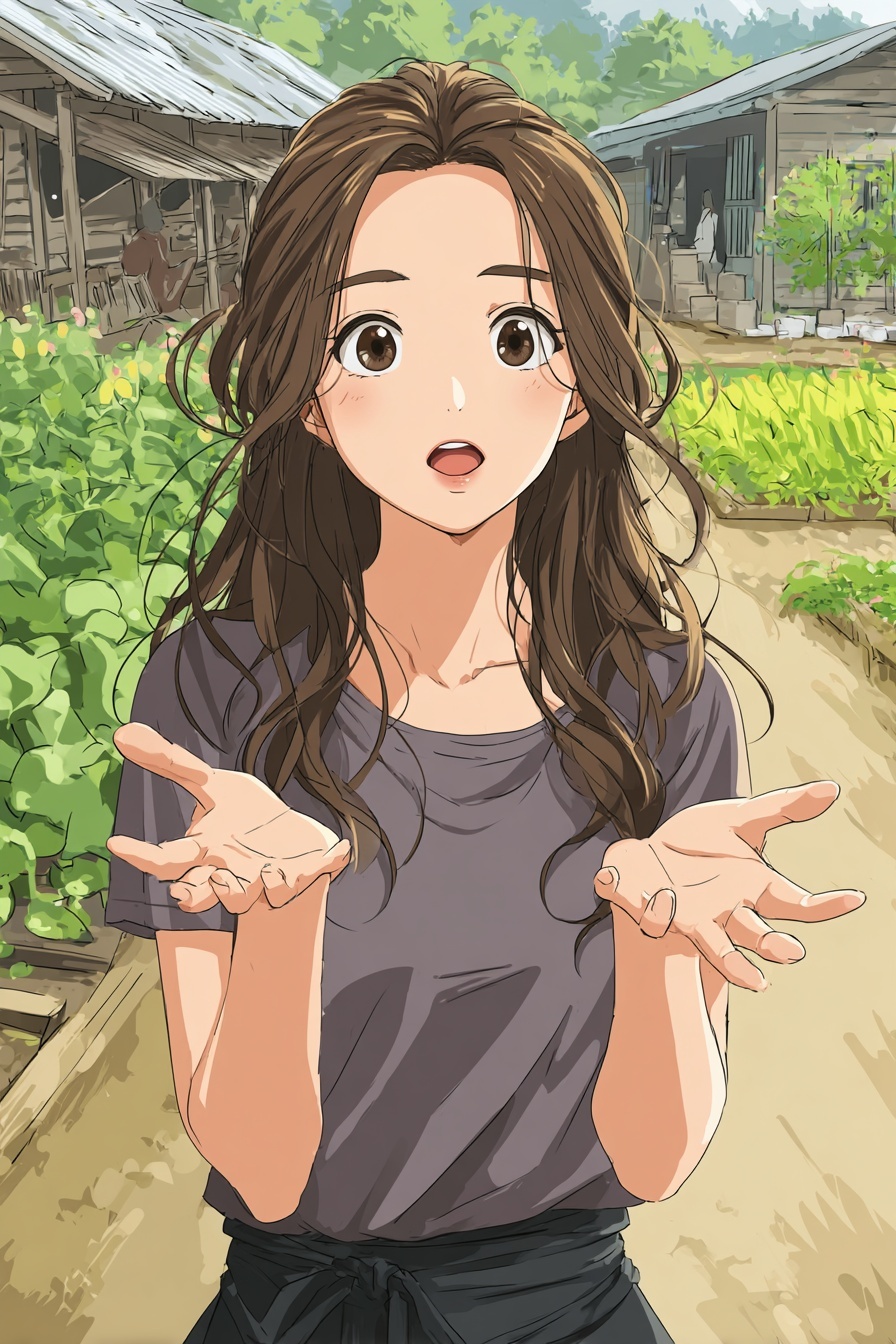瑞相御書
建治元年(ʼ75) 54歳 (四条金吾)
背景と大意
この書は建治元年(1275年)、日蓮大聖人が五十四歳の時に身延で認められたものである。末尾の部分が欠落しているため、誰に宛てられたかは明らかでないが、一般には、武士であり大聖人の最も忠実な門弟の一人である四条金吾に送られたものと考えられている。当時、四条金吾はその信仰ゆえに主君や同僚の武士たちから強い反対に直面していた。
文永11年(1274年)10月、蒙古軍が日本南部に大規模な襲撃を仕掛けた。翌年、フビライ・ハーンは再び使者を派遣し、日本政府が元への服属を認めなければ再侵攻すると脅した。『瑞相御書』(On Omens)は、この蒙古の脅威や近年の災難を、大聖人の教えに照らして解釈している。
この書の冒頭において、大聖人は釈尊が『法華経』を説いた際に現れた瑞相を「生命と環境は一体である」(依正不二)という原理から論じている。そしてこの原理をさらに展開し、人々の六根、すなわち感覚器官が迷いに覆われると、天地に異常な変化が生じるのだと説く。これは、生命と環境が二つの独立した現象のように見えても、根本的には一体・不二であるという真理を示しているのである。
次に大聖人は、仏の説法には必ず先立って瑞相が現れることを述べる。その瑞相の大きさは、これから説かれる教えの深さを反映している。ゆえに『法華経』を説く際に現れた瑞相は、他のどの経典に先立つ瑞相よりも偉大であった。さらに、『法華経』の前半である迹門に先立つ瑞相よりも、後半である本門を導く瑞相のほうがはるかに勝れていたのである。大聖人は、宝塔の出現や地涌の菩薩の出現を、迹門に勝る本門の尊さを示す瑞相として挙げている。さらに「神力品」の大瑞はそれすらも超えており、「寿量品」の奥深くに示された南無妙法蓮華経の法が末法に広く弘まることを予告しているのだと述べる。
そして大聖人は、己の時代の日本における動乱や異変に話を移す。それらすべては、末法において法華経の肝要を弘める行者に人々が敵対しているがゆえに起こるのだと結論づける。特に、大聖人は、念仏・真言の僧侶たちの誹謗によって、日本は外敵に滅ぼされるであろうと警告する。そしてまた、人々は「正しい教えを抱く一僧」(すなわち大聖人自身)を迫害しているために、大災難に苦しんでいるのだと述べるのである。このようにして大聖人は、弟子に対して自身の教えの正しさを確信させ、また迫害が必然であることを強調している。
第一章(依正不二の原理を説く)
本文
夫れ、天変は衆人をおどろかし、地夭は諸人をうごかす。仏、法華経をとかんとし給う時、五瑞六瑞をげんじ給う。その中に地動瑞と申すは、大地六種に震動す。六種と申すは、天台大師、文句の三に釈して云わく「東涌西没とは、東方は青、肝を主る。肝は眼を主る。西方は白、肺を主る。肺は鼻を主る。これ眼根の功徳生じて鼻根の煩悩互いに滅することを表すなり。鼻根の功徳生ぜば、眼の中の煩悩互いに滅す。余方の涌没して余根の生滅を表すことも、また」云々。妙楽大師、これを承けて云わく「根を表すと言うは、眼・鼻はすでに東西を表す。耳・舌は理として南北に対す。中央は心なり。四方は身なり。身に四根を具す。心はあまねく四を縁ず。故に、心をもって身に対して涌没となす」云々。
夫れ、十方は依報なり、衆生は正報なり。依報は影のごとし、正報は体のごとし。身なくば影なし、正報なくば依報なし。また正報をば依報をもってこれをつくる。眼根をば東方をもってこれをつくる。舌は南方、鼻は西方、耳は北方、身は四方、心は中央等、これをもってしんぬべし。かるがゆえに、衆生の五根やぶれんとせば、四方・中央おどろくべし。されば、国土やぶれんとするしるしには、まず山くずれ、草木かれ、江河つくるしるしあり。人の眼・耳等驚そうすれば天変あり、人の心をうごかせば地動ず。
現代語訳
天の異変は多くの人を驚かし、大地の災厄はもろもろの人を動揺させる。仏は法華経を説こうとされたときに、五瑞六瑞をあらわされた。その六瑞の中の地動瑞というのは、大地が六種に震動することである。この六種の震動というのは、天台大師が法華文句の第三に「東方が高く盛り上がり西方が低く沈んだというのは、東方とは青色で肝蔵をつかさどり、肝蔵は、また眼をつかさどる。西方は白色で肺蔵をつかさどり、肺蔵は、また鼻をつかさどる。それゆえ、東涌西没とは、眼根の功徳が生じて、それに応じて鼻根の煩悩が滅することを表わしている。鼻根の功徳が生じ、これに応じて眼の中の煩悩が滅する。その他の方角の涌没によって、それに関係する余根の功徳、煩悩の生滅を表わすのもこれと同じである」と説いている。
妙楽大師は、これを受けて「各方角が六根を表わすというのは眼と鼻が已に東西を表わしているのであるから、耳と舌は道理として南北に対応する。中央は心である。四方は身である。身は四根を具し、心は徧く四根に縁している。ゆえに、心は身に対し涌没を起こさせるのである」と解している。
十方は依報である。衆生は正報である。依報は、たとえば影であり、正報は体である。身がなければ影はない。と同じく正報がなければ依報もないのである。また、その正報は、依報をもってその体を作る。眼根は東方によって作られる。と同じく舌は南方、鼻は西方、耳は北方、身は四方、心は中央に対応することは、これによって知ることができよう。それ故、衆生の五根が破れようとするときは、四方や中央の地が動くのである。したがって国土がまさに崩壊しようとする前兆として、まず山が崩れ、草木が枯れ、河川の水が涸れ尽きてしまう。また、人の眼や耳等が驚き騒げば、天変が起こり、衆生の心を動かせば大地が震動するのである。
語釈
天変
天空に起こる異変。暴風雨・日蝕・月蝕等。
地夭
地上に起こる異変。
六瑞
法華経序品第一に、法華経が説かれる瑞相として、六種の瑞相が現われたと説かれている。これに此土の六瑞と他土の六瑞がある。
此土の六瑞とは、
①説法瑞。 無量義経を説き終わっても聴衆は去らないで後説を待ち続けた。
②入定瑞。 仏が無量義経を説き終わって、無量義処三昧に入った。
③雨華瑞。 そのときに天より曼荼羅華等の四種の華を雨らせた。
④地動瑞。 雨華瑞のあと大地が六種に震動した。
⑤衆喜瑞。 これを見た大衆が内心に歓喜を生じた。
⑥放光瑞。 仏の眉間の白毫より光りを放って、東方八千の仏土を照らして、そこに現じた瑞を見た。
また、他土の六瑞とは、
①見六趣瑞。 白毫相の光により、仏が阿鼻地獄より阿迦尼吒天に至る六界の衆生を見る。
②見六諸仏瑞。 六趣それぞれの土の諸仏を見る。
③聞諸仏説法瑞。その諸仏の説法を聞く。
④見四衆得道瑞。そのそれぞれの仏によって、諸の比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷の四衆が得道するのを見る。
⑤見菩薩所行瑞。諸の菩薩摩訶薩の菩薩道を行ずるのを見る。
⑥見仏涅槃瑞。 諸仏の般涅槃したのを見る。
地動瑞
序品の文。「諸仏世界六種に振動す」と読む。前文を引くと次の通り。「諸の菩薩の為に、大乗経の、無量義、教菩薩法、仏所護念と名くるを説きたもう。仏、此の経を説き已って、結跏趺坐し、無量義処三昧に入って、身心動したまわず。是の時に、天より曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華を雨らして仏の上、及び諸の大衆に散じ、普仏世界六種に震動す」
天台大師
(0538~0597)。智顗のこと。中国の陳・隋にかけて活躍した僧で、中国天台宗の事実上の開祖。智者大師とたたえられる。大蘇山にいた南岳大師慧思に師事した。薬王菩薩本事品第23の文によって開悟し、後に天台山に登って一念開悟し、円頓止観を悟った。『法華文句』『法華玄義』『摩訶止観』を講述し、これを弟子の章安大師灌頂がまとめた。これらによって、法華経を宣揚するとともに観心の修行である一念三千の法門を説いた。存命中に陳・隋を治めていた、陳の宣帝と後主叔宝、隋の文帝と煬帝(晋王楊広)の帰依を受けた。
【薬王・天台・伝教】日蓮大聖人の時代の日本では、薬王菩薩が天台大師として現れ、さらに天台の後身として伝教大師最澄が現れたという説が広く知られていた。大聖人もこの説を踏まえられ、「和漢王代記」では伝教大師を「天台の後身なり」とされている。
五根
目・耳・鼻・舌・身のことをいう。根とは、生命には、対境に縁すると作用する機能が本然的に備わっており、その機能の根源を根という。たとえば、生命には眼根があるため、色境に縁すれば眼識を生ずるのである。
講義
本抄は、建治元年(1275)、54歳の時に書かれたものである。末尾が欠けているため、誰に与えられたものであるかは不明であるが、四条金吾というのが一般に認められている説である。
内容は、仏が法華経を説くにあたって起こった瑞相を取り上げ、末法流布の付嘱の儀式である神力品の際の瑞相がひときわ勝れていることを指摘されている。そして、特にこの瑞相の中でも大地が動いたということは、人の六根を動ずることの象徴であり、末法に妙法を弘めることが、いかに大きい波動を起こすものであるかを、現実の様相をあげて示されている。
瑞相として経文に説かれているのは、自然界に起こる異変であるが、自然界と人間生命とが、依正不二の関係にあることを明かされており、本書は、そうした生命の不可思議の実相を解明されている書として、深遠な内容を包含している。
夫れ十方は依報なり、衆生は正報なり。譬へば依報は影のごとし、正報は体のごとし。身なくば影なし、正報なくば依報なし。又正報をば依報をもって此れをつくる
衆生とは生命活動を行なっている主体である。十方とは、先の東西南北等をうけて、このように表現されたのであって、国土、宇宙という意である。この生命主体と国土・宇宙との関係は、正報と依報との関係になる。
正報とは、果報を現ずる主体であり、依報は、その正報の依る所である。したがって、この正報と依報との関係は、正報を体とすると、依報はその影のようなものである。だが、では依報は、実在性のない幻のようなものかというと、そうではなく、依報によって正報は作られるのである。
生命体は、物質的にも精神的にも、常に外界から必要なものを採り入れ、それによって活動を維持している。肉体を形成する物質は当然のこと、生命活動を維持するための空気、水などは、一瞬たりとも補給の欠かせない物質である。精神活動もまた、外界の絶え間ない刺激を受けて、健全な活動が行なわれるのである。外界の刺激が全く遮断された状況におかれると、精神活動は幻想を見るようになり、異常をきたすことは、幾多の実験によって明らかにされている通りである。
生命活動は、その主体性、自律性に非生命的現象と区別される特質がある。つまり、最も単純な原始的生命も、自らを維持しようとする機能を有し、種属を維持する方法をもっている。そして、積極的に外界に働きかけ、そこから、自己の目的に必要な物質を摂取する。この生命活動の主体的機能についてみると、まさに、正報は〝体〟であり、依報は〝影〟である。
〝報〟というものは、もともと生命活動のメカニズムのようなものであるから、正報がなければ、依報ということもありえない。故に「身なくば影なし、正報なくば依報なし」といわれているのである。しかしながら、その逆に、依報によって正報は成り立つのであるから、依報のない正報はありえないのである。この正報と依報の関係を依正不二というわけである。
だが、ここに述べられている正報と依報の関係は、更に深く、微妙である。すなわち、正報の心の中の変動が、依報の異変をもたらすという原理である。ここでは、依報は正報を映す鏡のようなものとして把えられている。人の心の中の変動は、外から容易に見ることができない。個人の心の表面的・日常的な動きは、その表情の変化によって知ることができるが、社会全体の人々の心に起こった深層の激変は、顔などの表情を通しては把握できない。その巨大な深部の変動は、依報の鏡に映り、すなわち天変地夭として初めて知ることができるというのである。
この生命の深層の真理は、凡智をもって理解することは難しい。ただ、仏法の法理と、透徹した仏の英知の直観力によってのみ、その実態を把握できるものなのであろう。「衆生の五根やぶれんとせば、四方中央をどろうべし。されば国土やぶれんとするしるしには、まづ山くづれ、草木かれ、江河つくるしるしあり。人の眼耳等驚そうすれば天変あり。人の心をうごかせば地動ず」と仰せられているのが、これである。
第二章(法華経の瑞相を明かす)
本文
抑何の経経にか六種動これなき一切経を仏とかせ給いしにみなこれあり、しかれども仏法華経をとかせ給はんとて六種震動ありしかば衆も・ことにおどろき弥勒菩薩も疑い文殊師利菩薩もこたへしは諸経よりも瑞も大に久しくありしかば疑も大に決しがたかりしなり、故に妙楽の云く「何れの大乗経にか集衆・放光・雨花・動地あらざらん但大疑を生ずること無し」等云云、此の釈の心はいかなる経経にも序は候へども此れほど大なるはなしとなり・されば天台大師の云く「世人以蜘蛛掛れば喜び来り干鵲鳴けば行人至ると小すら尚徴有り大焉ぞ瑞無からん近きを以て遠きを表す」等云云。
夫一代四十余年が間なかりし大瑞を現じて法華経の迹門を・とかせ給いぬ、
現代語訳
一体どの経に六種動がなかったという例があろうか。一切経を仏が説かれた時に、みな六種動はあった。しかし仏が法華経を説かれようとしたときの六種震動には、衆生もことに驚き、弥勒菩薩も疑問を発し、文殊師利菩薩がそのことに答えたのは諸経よりも瑞が大きく長かったので、疑いも大きく晴らしがたかったからである。故に妙楽は「何れの大乗経にも集衆・放光・雨花・動地等の瑞相がない例はないが、ただし人々がこのような大なる疑いを起こしたことはなかった」といっている。この釈は、いかなる経々にも序として瑞相というものがあるが、この法華経のような大きな瑞相を伴ったものはないという意である。
故に天台大師も「世間の人は『蜘蛛が巣をかければ近く喜びごとが訪れ、鳱鵲が鳴けば客人が来る』という。このように世間の小事ですら前兆があるのであるから、まして仏法の大事にどうして瑞相のないことがあろうか。瑞相という近くに見えるものをもって、仏法の深遠の道理を表わすものである」と説いている。
釈尊は一代四十余年の間、かってなかった大瑞相を現わして法華経の迹門を説かれたのである。
語釈
弥勒菩薩
慈氏と訳し、名は阿逸多といい無能勝と訳す。インドの婆羅門の家に生れ、のちに釈尊の弟子となり、慈悲第一といわれ、釈尊の仏位を継ぐべき補処の菩薩となった。釈尊に先立って入滅し、兜率の内院に生まれ、五十六億七千万歳の後、再び世に出て釈尊のあとを継ぐと菩薩処胎経に説かれている。法華経の従地涌出品では発起衆となり、寿量品、分別功徳品、随喜功徳品では対告衆となった菩薩である。
文殊師利菩薩
文殊菩薩のこと。菩薩の中では智慧第一といわれる。法華経序品では過去の日月灯明仏のときに妙光菩薩として現われたと説かれている。迹化の菩薩の上首で、普賢菩薩と対で権大乗の釈尊の左に座した。文殊菩薩を生命論から約せば、普賢菩薩が学問を究め、真理を探究し、法理を生み出す智慧、不変真如の理、普遍性、抽象性の働きであるのに対し、文殊菩薩の生命は、より具体的な生活についての隨縁真如の智、特殊性、具象性の智慧の働きをいう。
干鵲
カササギのこと。カラスより少し小さく、腹白で頭部が黒い。日本では北九州にいる。高麗烏といわれる。
迹門
本門の対語で、垂迹仏が説いた法門の意。法華経二十八品中の序品第一から安楽行品第十四までの前十四品をさす。内容は、諸法実相、十如是の法門のうえから理の一念三千を説き、それまで衆生の機根に応じて説いてきた声聞・縁覚・菩薩の各境界を修業の目的とする教法を止揚し、一切衆生を成仏させることにあるとしている。しかし釈尊が過去世の修行の結果、インドに出現して始めて成仏したという、迹仏の立場であることは爾前と変わらない。
講義
法華経が、それ以前の諸経に超過する高度な哲理を説いていることを、瑞相の大きさで論じられている段である。
もちろん、こうしたことは、仏法を信ずる心のない人にとっては、あまり意味のない問題かも知れない。まして、法華経にそのような大瑞があったという意味のことが説かれていたとしても、我田引水に過ぎないのではないかという反論も出てこよう。しかも、今日においては、仏教学者の中にも、大乗仏教――したがって法華経も含んで――は、釈迦自身が説いたものでなく、後世になってつくられたものだとする説さえ有力である。
もちろん、こうした説に対して、たしかに釈迦が説いたのだと反論できる証拠はない。たとえ、釈迦でない誰かが、後世になって説いたにせよ、大事なことは、法華経が、いかにすぐれた哲理を説き示しているか、である。
仏教が、他のいかなる宗教も果たし得なかった偉大な真理を究明しているといえるのは、なんといっても、生命の哲理を余すところなく説ききっていることである。それは、法華経のみが解明しているところである。そして、この生命の正しい把握の上に立って、人間自身と、社会の変革、ひいては国土・自然の本源的変革の原理を示したのである。
もし、法華経があらわれなかったら、仏教は、現実を否定して、虚無におちいってしまうか、西方極楽浄土の幻想を追い求めて、現実から逃避する思想でしかなかったであろう。もちろん、それでも、そこに至る論理的組み立ての完璧さ、事実の分析的手法の鋭さは、キリスト教やイスラム教などの、遙かに及ばない、優れたものを持ってはいる。だが、それだけに、救いようのない虚無主義や逃避思想に我が身を縛る結果となる。
法華経がはじめて、この法華以前の経々がもっていた歪みを是正し、ある意味では百八十度転換して、現実に生きる人間の、この生における本質的救済の宗教としたのである。ただし、ここで注意しなければならないのは、この結論のみに目を奪われて、あたかも、法華経が、それ以前の経々のもっていた事相の分析や論理的組み立ての完璧なまでの見事な諸成果を否定してしまったと考えるのは早計であり、浅薄であるということだ。
法華経は、これらを同じ次元で否定し崩壊せしめたのではなく、それらを全て生かしつつ、より深い次元の真理に目を開くことにより、一切を包摂し、止揚しているのである。すなわち、究極の理想の境地である仏界を、法華経以前の大乗教では、この世界を遙かに離れた極楽浄土等にあると説いた。法華経にいたってはじめて、それが、この現実に生きる衆生の生命の内にあると説いたのである。
それは、仏界の境地のすばらしさを否定するものではない。また、崇高な理想をめざして前進しようとする姿勢を拒否するのでもない。法華経以前に説いたことは当然の前提としつつ、そうした理想を現実のものとする確固たる法理を解明したのが法華経である。
また、法華経は、仏界という、絶対的な幸福境涯を教えるが、それは、たとえば小乗経で展開している、人間の苦悩への精緻な分析と洞察に比べて、あまりにも背反しているように考えられやすい。小乗経典の分析が知性的であるのに対し、法華経の教説は反知性的であるように思われるかも知れない。だが、法華経の大胆な結論は、小乗教等の細心の分析から離れて下されているのではなく、その根底は、確実にこれらの内容を踏まえて、説き明かしているのである。
ここに、法華経が、それ以前の全ての経典を凌駕する卓越性があるのであって、それは瑞相などを神秘的な装飾として信じられぬという人も、認めざるを得ないところであろうと確信する。法華経が、こうした瑞相を挙げているのは、当時の人々にとっては理解しやすかったのと同時に、より深い意味では、そのような事相が、その奥底に不変の真理をあらわしていたのである。つまり、地動瑞とは、人々の心を動かし、社会を動かすということを、譬喩的に示しているわけである。これは秘妙方便という概念に属するものであり、したがって、やはりこれらの瑞相は、いかに非科学的に見えようと、落とすことのできない要素であったのである。
第三章(本門の瑞相を説く)
本文
其の上本門と申すは又爾前の経経の瑞に迹門を対するよりも大なる大瑞なり、大宝塔の地より・をどりいでし地涌千界・大地よりならび出でし大震動は大風の大海を吹けば大山のごとくなる大波のあしのはのごとくなる小船のをひほにつくが・ごとくなりしなり、されば序品の瑞をば弥勒は文殊に問い涌出品の大瑞をば慈氏は仏に問いたてまつる・これを妙楽釈して云く「迹事は浅近・文殊に寄すべし久本は裁り難し故に唯仏に託す」云云・迹門のことは仏説き給はざりしかども文殊ほぼこれをしれり、本門の事は妙徳すこしもはからず、此の大瑞は在世の事にて候、仏・神力品にいたつて十神力を現ず此れは又さきの二瑞には・にるべくもなき神力なり、序品の放光は東方・万八千土、神力品の大放光は十方世界、序品の地動は但三千界・神力品の大地動は諸仏の世界・地皆六種に震動す、此の瑞も又又かくのごとし、此の神力品の大瑞は仏の滅後正像二千年すぎて末法に入つて法華経の肝要のひろまらせ給うべき大瑞なり、経文に云く「仏の滅度の後に能く是の経を持つを以ての故に諸仏皆歓喜して無量の神力を現ず」等云云、又云く「悪世末法の時」等云云。
疑つて云く夫れ瑞は吉凶につけて或は一時・二時・或は一日・二日・或は一年・二年・或は七年・十二年か・如何ぞ二千余年已後の瑞あるべきや、答えて云く周の昭王の瑞は一千十五年に始めてあえり、訖利季王の夢は二万二千年に始めてあいぬ、豈二千余年の事の前にあらはるるを疑うべきや、
現代語訳
更にその上、法華経本門が説かれたときの瑞相は、爾前の経々の瑞相に迹門の瑞相を比べたよりもはるかに大きい瑞相であった。宝塔品において大宝塔が大地から涌現したり、次の涌出品になって地涌千界の大菩薩が大地から多数涌出したときの大震動は、ちょうど大風が大海に吹きつけて大山のような波を起こし、その波が蘆の葉のような小船を襲い、帆まで浸すような、大きな震動だったのである。
ゆえに、序品の瑞相については弥勒菩薩が文殊師利菩薩に質問したのに対し、涌出品の大瑞については慈氏が仏に質問したのである。これを妙楽は文句記の三に釈して「迹門の事は浅近の法なるがゆえに文殊師利菩薩に委ねた。久遠の本地は解し難いゆえにただ仏に託したのである」と述べている。迹門の瑞相については仏は説かなかったが、文殊はだいたいこの意義を知っていた。ところが本門のことは、妙徳は少しも推量できなかったのである。ただし、この大瑞は釈迦在世のことである。
仏は、更に神力品にいたって十神力を現じた。これはさきの序品や宝塔・涌出品の二瑞とは比較にならない神力である。序品のときの放光は東方万八千土の国土を照らしたにとどまったが、神力品の大放光は十方の世界にまで及んだ。また、序品の地動瑞は、ただ三千世界に限られていたが、神力品の大地動は十方の諸仏の全世界において、大地が六種に震動したのである。この瑞相もまた同様である。
この神力品の大瑞相は仏滅後、正像二千年が過ぎて、末法に入り法華経の肝要が広まるという大瑞相である。法華経神力品には「仏の滅後に衆生が能くこの経を持つことによって諸仏はみな歓喜して、無量の神力を現わすのである」と説かれている。また、分別功徳品には「悪世末法の時」と説かれている。
疑っていうには、瑞相は吉瑞凶瑞いずれにしても、一時二時、あるいは一日二日後、または一年二年後か、七年十二年後のことを示すものはあるが、どうして二千余年も後世のことを知らす瑞相があるのであろうか。
答えていうには、昔、中国の周の昭王の瑞相は一千十五年後に始めて符合し、太古インドの訖利季王の夢は二万二千年後に始めて合致した。二千余年後のことが、前瑞としてあらわれたことを疑うにはあたらない。
語釈
大宝塔
法華経見宝塔品第十一に「爾の時、仏前に七宝の塔有りて、高さ五百由旬、縦広二百五十由旬にして、地従り涌出して、空中に住して」とある。この宝塔は、一応は迹門の説法の証明のためであるが、再応は本門の説法を起こす遠序としてあらわれたのである。ゆえに、宝塔品それ自体は迹門十四品の中に位置しているが、本文の瑞として挙げられているのである。
地涌千界
法華経従地涌出品第十五に「仏は是れを説きたまう時、娑婆世界の三千大千の国土は、地皆な震裂して、其の中於り無量千万億の菩薩摩訶薩有って、同時に涌出せり」とある。この地涌の菩薩の出現は、滅後末法の妙法流布の使命を託すためであるが、また、寿量品の仏の本地を示すための不可欠の前提となった。ゆえに、この地涌出現を、一応「在世の事」といわれているのである。
慈氏
弥勒菩薩のことで慈氏と訳し、名は阿逸多といい無能勝と訳す。インドの婆羅門の家に生れ、のちに釈尊の弟子となり、慈悲第一といわれ、釈尊の仏位を継ぐべき補処の菩薩となった。釈尊に先立って入滅し、兜率の内院に生まれ、五十六億七千万歳の後、再び世に出て釈尊のあとを継ぐと菩薩処胎経に説かれている。法華経の従地涌出品では発起衆となり、寿量品、分別功徳品、随喜功徳品では対告衆となった菩薩である。
妙徳
文殊師利菩薩の訳。文殊は妙の義、師利は徳の義。
神力品
妙法蓮華経如来神力品第21のこと。妙法の大法を付嘱するために、10種の神力を現じ、四句の要法をもって地涌の菩薩に付嘱する。別付嘱と結要付嘱ともいうことが説かれている。
十神力
十種の大力ともいう。釈迦は十種の神力を現じて、上行菩薩に深法を付嘱した、すなわち①出広長舌、「広長舌を出して上梵世に至らしめ」②通身放光、「一切の毛孔より、無量無数色の光を放って皆悉く徧くく十方世界を照したもう」③一時謦欬、「然して後に還って舌相を摂めて一時に謦欬し」④倶共弾指「倶共に弾指したもう」⑤地六種動、「是の二つの音声、徧く十方の諸仏の世界に至って、地皆六種に震動す」⑥普見大会、「其の中の衆生、天、竜、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦楼羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等、仏の神力を以ての故に、皆此の娑婆世界、無量無辺百千万億の衆の宝樹下の師子座上の諸仏を見、及び釈迦牟尼仏、多宝如来と共に宝塔の中に在して、師子の座に坐したまえるを見たてまつり、又、無量無辺百千万億の菩薩摩訶薩、及び諸の四衆の、釈迦牟尼仏を恭敬し囲繞したてまつるを見る」⑦空中唱声、「即時に諸天、虚空の中に於いて、高声に唱えて言わく」⑧咸皆帰命、「彼の諸の衆生、虚空の中の声を聞き已って、合掌して娑婆世界に向かって、是の如き言を作さく、南無釈迦牟尼仏、南無釈迦牟尼仏と」。⑨遙散諸物、「種々の華香、瓔珞、幡蓋、及び諸の厳身の具、珍宝、妙物を以って、皆共に遥かに娑婆世界に散ず」⑩十方通同、「時に十方世界通達無碍にして一仏土の如し」とある
神力品の大放光
法華経如来神力品第21には「一切の毛孔より、無量無数色の光を放って皆悉く遍く十方世界を照したもう」とある。
末法
正像末の三時の一つ。衆生が三毒強盛の故に証果が得られない時代。釈迦仏法においては、滅後2000年以降をいう。
法華経の肝要
日蓮大聖人建立の南無妙法蓮華経のこと。
周の昭王の瑞
周書異記にあるといわれる。昭王は中国古代・周の第四代の王。この昭王の24年の4月8日の夜中に五色の光気があらわれ、大地は六種に震動し、雨が降らないのに江河、井池の水があふれ出て、一切の草木に花が咲き、菓がなったという。王がこのことに驚き、大史蘇由に問うたところ、蘇由が答えていうには「西方の国に聖人が生まれた、その聖人の教えは一千年ののち、この中国に伝わってくるであろう」と。昭王はこのことを石に刻ませ、これを碑として建てた。この年月日は、ちょうど釈尊がインドに生まれた日に該当し、しかも、蘇由の予言どおり、1015年経った後漢の明帝の治世、永平10年(0067)に仏法はインドから中国に伝えられたという。
訖利季王の夢
守護国界主陀羅尼経巻第十の阿闍世王受記品第十にある。訖利季王は太古二万年前のインドの王で、迦葉仏の父。ある夜、王は二つの夢を見た。その一つは十匹の猿がいて、そのうちの九匹は城中の一切の人民、男女を擾乱して、飲食を侵奪し、器物を破壊した。ところが一匹だけ心に知足を懐いて、樹上に安座して人を乱すことはしなかった。他の九匹は、この一匹をいじめて、仲間から追い払った。もう一つの夢は、一匹の白象があり、首と尾に口があり、水草をみな食べ、つねに飲食しながら、しかもその身はつねに痩せていた。この二つの夢について、訖利季王が迦葉仏に質問したところ、迦葉仏は、この夢は五濁悪世に仏が出現し、その仏の滅後の遺法の相を示すものだと答えた。その仏は釈迦牟尼仏と称し、十匹の猿は、釈迦牟尼仏の十種の弟子であり、その中の一匹が少欲知足で独り樹上にいて、人を擾さないのは、釈迦如来遺法中の沙門であると教えた。また第二の白象の夢については、王の家臣が寵愛と栄禄をむさぼり、非理の追及を行なって、ついに家をほろぼし、身を破り、今度は仏法に出家すると、悪比丘となって邪見を起こして外道になることを示すものだと説いたという。
講義
法華経の迹門と本門とを相対して、本門が迹門に対してはるかに勝れていることを、その瑞相の大きさの違いから示し、更に、同じ本門のための瑞相でも、在世に属する宝塔・涌出両品の瑞相と、一向に滅後末法のための神力品の瑞相との違いを指摘されている段である。
大宝塔の地よりをどりいでし、地涌千界大地よりならび出し大震動
宝塔涌現および地涌千界涌出の様子については、語訳に示した通りである。この文では、これらを、いずれも在世の本門の瑞相として挙げられている。
滅後末法の大法である文底下種の法門から立ち返ってみるならば、これらの儀式といい、迹門の説法といい、更には爾前権教の所説といっても、全て滅後末法のためといえる。なかんずく、宝塔の涌現は、末法流布の正体である三大秘法の大御本尊をあらわすためであり、地涌の出現は、末法弘通の使命を付嘱するためであるから「在世の事」というより「滅後の事」というべきであるようにさえ思われる。
しかし、一応、経文の順序からいえば、宝塔涌現は、一に証前すなわち迹門の真実であることを証明するためであり、二に起後すなわち本門の説法の準備のためであった。ゆえに、在世本門の瑞相として扱われているのである。また、地涌千界の涌出も、一応は本門の釈尊の久遠の弟子として、五百塵点の遠寿をあらわすための補佐としてあらわれている。したがって、これも、在世本門の瑞相という扱いがされているのである。
これに対し、神力品は、その文上の意味からいっても、全く滅後末法の付嘱の儀式であって、完全に在世のためではなく滅後のためである。ゆえに、神力品の十神力の瑞相を、末法に大白法を流布すべき前兆とされているわけである。
迹門のことは仏説き給はざりしかども文殊ほぼこれをしれり。本門の事は妙徳すこしもはからず。此の大瑞は在世の事にて候
迹門は、在世の衆生を得脱せしめるための法であり、声聞を代表とする一切衆生の生命の内に仏知見が具わっていることを明かした哲理である。文殊は、釈迦の九代前の師であったほどの智者であるから、これぐらいの真理は、仏が説かなくとも、前もって知ることができた。ゆえに、序品の瑞相が起こったときに、弥勒が質問を発したのに対し、文殊はそれに答えることができたのである。
しかるに、本門は、滅後末法の衆生のために大仏法をあらわそうとした儀式であり、仏自身が久遠の昔に証得した仏界の境地を説くのである。これは、まだ菩薩の位でしかない文殊師利菩薩にとっては、推し測ることさえ不可能である。したがって、文殊は、本門の瑞相の意味については答えることができず、ただ仏がこれを明かしたという形をとっているのである。
ここに、迹門と本門との違いが、明確に指摘されている。迹門は、在世の衆生を得脱させるため、まだ、仏の本地を明かさず、多分に化他の様相を帯びている。これに対し、本門は、仏の本地を解明し、その仏の悟りをそのまま、生命の儀式として展開した。この仏の悟りこそ「法華経の肝要」となるもので、それを滅後末法のため、本化の弟子、実は久遠元初の自受用身に付嘱する儀式が行なわれるのである。
仏、神力品にいたって十神力を現ず。此れは又さきの二瑞にはにるべくもなき神力なり
「さきの二瑞」とは、迹門のための序品の瑞相と、在世本門のための宝塔・地涌の瑞相との二つと考えられる。
ところで、序品の六瑞とは、
1・説法瑞、
2・入定瑞、
3・雨華瑞、
4・地動瑞、
5・衆喜瑞、
6・放光瑞、
であり、これを「此土の六といい、他に「他土の六瑞」すなわち
1・見六趣瑞、
2・見諸佛瑞、
3・聞諸佛説法瑞、
4・見四衆得道瑞、
5・見菩薩修行瑞、
6・見諸佛涅槃瑞、
がある。神力品の十神力とは、
1・吐舌相、
2・通身放光、
3・一時謦欬、
4・俱共弾指、
5・地六種動、
6・普見大会、
7・空中唱声、
8・咸皆帰命、
9・遙散諸物、
10・十方通同
である。
この序品の六瑞と神力品の十神力とは、共通するものが幾つかあるが、それを較べてみるとき、一見、同じようであっても、その規模の大きさが全く違うことが理解される。
序品の地動瑞は「普き仏の世界は六種に震動す」、「此の世界は六種に振動す」とあるのみである。涌出品の地涌千界出現のときの大地の振動については「娑婆世界の三千大千の国土は、地皆な震裂して、其の中於り無量千万億の菩薩摩訶薩有って、同時に涌出せり」とある。これに対し、神力品の地六種動は「一時に謦欬し、倶共に弾指したまう。是の二つの音声は、遍く十方の諸仏の世界に至って、地は皆な六種に震動す」とあるように、十方世界にわたっている。
放光に関しても、序品の放光瑞は「爾の時、仏は眉間白毫相の光を放ちて、東方の万八千の世界を照らしたまうに、周遍せざること靡し」とある。それに対し、神力品の通身放光は「一切の毛孔より、無量無数色の光を放って、皆悉な遍く十方世界を照らしたまう」とある。
このように、序品の時の瑞相が「此の世界」や「東方万八千の国土」に限られているのに対し、神力品の瑞相がいずれも十方世界に行きわたったというのは、迹門の仏がまだ始成正覚の垂迹の仏であるのに対し、本門の仏は久遠の本地をあらわした仏であるという、力の勝劣を示している。また、当然、そこにあらわされる迹門の法と、本門の法との歴然たる力の相違をも表象しているのである。特に、神力品のあらわそうとした法は、すでに末法の大法であり、南無妙法蓮華経そのものである。ゆえに、これは十方世界すなわち全宇宙を包含する広大深遠の力をもっているのである。
また、本地は久遠元初の無作三身である地涌の出現によって震裂したのが「娑婆世界の三千大千の国土」に限られていたというのは、あくまでも垂迹の地涌の菩薩として出現したのであるから、これもまた、当然のことといわなければならないであろう。なお、放光とは、仏の智慧の働き、徳用が人々の心の闇を晴らすという姿を表象したものであり、大地の震動とは、人々の心に動執生疑を起こし、既成の価値観が崩壊し、正法にめざめていく姿を象徴したものと考えることができる。
第四章(末法の大瑞の本質を明かす)
本文
問うて云く在世よりも滅後の瑞・大なる如何、答えて云く大地の動ずる事は人の六根の動くによる、人の六根の動きの大小によつて大地の六種も高下あり、爾前の経経には一切衆生・煩悩をやぶるやう・なれども実にはやぶらず、今法華経は元品の無明をやぶるゆへに大動あり、末代は又在世よりも悪人多多なり、かるがゆへに在世の瑞にも・すぐれて・あるべきよしを示現し給う。
疑つて云く証文如何、答えて云く而かも此の経は如来の現在にすら猶怨嫉多し況や滅度の後をや等云云、去る正嘉・文永の大地震・大天変は天神七代・地神五代は・さてをきぬ、人王九十代・二千余年が間・日本国にいまだなき天変地夭なり、人の悦び多多なれば天に吉瑞をあらはし地に帝釈の動あり、人の悪心盛なれば天に凶変地に凶夭出来す、瞋恚の大小に随いて天変の大小あり地夭も又かくのごとし、今日本国・上一人より下万民にいたるまで大悪心の衆生充満せり、此の悪心の根本は日蓮によりて起れるところなり、
現代語訳
問うていうには、在世の瑞相よりも滅後の瑞相のほうが大きいのはなぜか。
答えていうのには、大地が動くのは人の六根が動くからである。したがって人の六根の動きの大小によって大地の六種の震動も高低がある。爾前の諸経は一切衆生の六根の煩悩を破っているようであるが、実際は、破っていない。今、法華経は、煩悩の最も根本である元品の無明を破るから大震動があるのである。しかも、末法は、在世よりも悪人が多い。その無明を破るのであるから、末法のための瑞相は、在世の瑞相よりも大きいということを仏は示し現わしているのである。
疑っていうには、末法には特に悪人が多いという証文はどこにあるのか。
答えていうには、それは法華経の法師品に「この経を弘通しようとすれば、如来の在世であっても怨嫉が多い。ましてや滅度の後においてはなおさらである」と説かれている。
去る正嘉の大地震、文永の大天変は、天神七代・地神五代といった神代の時代は別として、人王九十代・二千余年の間というもの、日本国にいままでなかった天変地夭である。
人の悦びが多ければ天には吉瑞が現われ、地には帝釈天の地動瑞が起こる。逆に人々の悪心が盛んになれば、天には不祥の異変が現われ、地には不吉な災厄が起こる。また人間の懐く瞋恚の大小によって、その現われる天変や地夭にも大小がある。現在の日本国には上一人より下万民に至るまで大悪心の衆生が充満している。この悪心の根本は日蓮によって起こったものである。
語釈
煩悩
貧・瞋・癡・慢・疑という人間が生まれながらに持っている本能。
元品の無明
生命に本来そなわった根本の迷い。一切の煩悩、悪業等はここから起こる。元品とは生命の本質という意味で、無明は三惑の一つ。釈迦仏法では万法の本質である中道法性を障える一切の生死煩悩の根本とし、別教では菩薩の断ずべき無明を十二品たてる。円教では、更に四十二品を立てている。この四十二品のうち、最後の無明惑を元品の無明といい、これを断じ尽くせば仏になれるとしている。
正嘉・文永の大地震・大天変
正嘉元年(1273)8月23日の大地震と文永元年(1264)6~8月、の大彗星のこと。呵責謗法滅罪抄(1192)に「正嘉元年太歳丁巳八月二十三日戌亥の刻の大地震と、文永元年太歳甲子七月四日の大彗星」とある。
正嘉の大地震は吾妻鏡巻四十三にはその時の模様が次のように記されている。「二十三日、乙巳、晴。戌刻大地震。音有り。神社仏閣一宇として全きは無し。山岳頽崩す。人屋顚倒す。築地皆悉く破損す。所々地裂け水涌き出す。中下馬橋辺の地裂け破れ、その中より火炎燃え出ず。色青し云々」。
文永の大彗星は、「文永の長星」ともいわれる。文永元年(1264年)6月26日に東北の上空に彗星が出現し、7月4日に再び現れ、8月に入っても光は衰えなかった。このため、彗星を攘う祈禱が連日のように行われたという。「安国論御勘由来」には「又其の後文永元年甲子七月五日彗星東方に出で余光大体一国土に及ぶ、此れ又世始まりてより已来無き所の凶瑞なり内外典の学者も其の凶瑞の根源を知らず」(0034)とある。
天神七代
地神五代より前に高天原に出た七代の天神。陽神(男神)と陰神(女神)がある初めは抽象的だった神々が、次第に男女に別れ異性を感じるようになり、最終的には愛を見つけ出し夫婦となる過程をもって、男女の体や性が整っていくことを表す部分だと言われている。①国常立神②国狭槌尊③豊斟渟尊(以上、独化神三世代)④泥土煮尊・沙土煮尊⑤大戸之道尊・大苫辺尊⑥面足尊・惶根尊 ⑦伊弉諾尊 ・伊弉冉尊。
地神五代
日本神話の神々。天神七代のあと地上に降りて人王第一代の神武天皇に先立って日本を治め、皇統の祖神となったとされる五代の神。日本書紀には天照大神、正哉吾勝勝速日天忍穂耳尊、天津彦火瓊瓊杵尊、彦火火出見尊、鸕鷀草葺不合尊をさす。
人王九十代
人王は神代に対して、神武天皇以後の天皇をいう。この建治元年(1275)当時の天皇は後宇多帝で、第九十一代とされる。
講義
大地の変動が人の六根の動きの反映であることは、本抄冒頭の、天台大師の文句に示されている通りである。爾前経は、その六根の汚濁をもたらす、生命の内にある煩悩を断尽することを説いた。
しかしながら、爾前経の煩悩断尽の法は、いわば枝葉を切るようなもので、根や幹にまで到らない。ゆえに、一つの煩悩を切ることによって、他のさまざまな煩悩を派生させていく。しかも、切ろうとした煩悩自体も、ますます盛んになって、却って手に負えないものになってしまう。
つまり、無数の煩悩を仏教では、大別して三惑に分けている。そのうち見思惑とは、事物の判断や思考の上に生ずる惑いであり、塵沙惑とは、生命の流転の上に累積してきた宿業である。だが、これらも、決局は、生命それ自体の本質につきまとう元品の無明が根幹となって現われているに過ぎない。
したがって、元品の無明を打ち破らなければ、煩悩のどす黒いエネルギーは、いつまでもなくならないばかりか、枝葉をいじればいじるほど、激しく出口を求めて噴出してくるのである。
では、元品の無明とは何か。本来、生命は一念三千であり、善悪無記である。その生命の実体を究め尽くし、境地冥合すれば、この生命を正しくリードし、惑いのない、赫々たる人生を歩むことができる。それを悟らずして、性悪の面である三悪道、四悪趣の生命に引きずられていけば、それは煩悩におおわれた人生とならざるを得ない。この、生命の実体を知らないのを元品の無明というのである。所詮、わが身妙法と開覚すれば、元品の無明は破れて、元品の法性とあらわれるのである。
法華経の教えの真髄は、一切衆生の生命に内在する仏界の生命を開覚することにある。すなわち、一切衆生をして、わが身即妙法の当体なりと覚知せしめることが、法華経の極意である。爾前経で教えてきた三惑を断じ、五欲を離れることは、この法華経の極理が成就されれば、おのずから達成される。むしろ五欲、煩悩は、この根本さえ転換されれば、生命活動の上に不可欠の五欲であり、煩悩はそのまま、生命の楽しみとなっていくのである。
ここで、六根と無明との関係について一言すると、六根のうち、中核をなすものが意根であり、全体を包含するのが身根である。これは、妙楽が「中央は心、四方は身」と約していることから明らかである。さて、意すなわち心、身すなわち色で、この色心の当体が生命である。この生命の拠って立つ姿勢、基盤が、元品の法性であり元品の無明であるわけだ。ゆえに、今の文で、六根の動きによって大地の動変があるといわれ「法華経は元品の無明をやぶるゆへに大動あり」(1141)と結論されているのである。
今日本国、上一人より下万民にいたるまで大悪心の衆生充満せり。此の悪心の根本は日蓮によりて起れるところなり
この前の「人の悦び多多なれば、天に吉瑞をあらはし……人の悪心盛んなれば、天に凶変……瞋恚の大小に随いて天変の大小あり云云」の文を受けて、現実の日本の様相を述べられているのである。もとより、それが、〝正嘉・文永の大地震・大天変〟の原因をなしていることを指摘されるためであることは、文の流れからいって当然である。
悪心にせよ善心にせよ、その心の激しさ、強さも大小の判定の大切な基準であるが、より重要な問題は、対象にある。いま、大聖人が〝大悪心〟といわれているのは、全民衆を救済しようとして、ただその広大な慈悲から起ち上がられた大聖人に対して、人々は憎悪と憤りをもって応えるのみであった。ゆえに、これは、大悪心という以外にないのである。
いわゆる大善に反対し、大善を憎むがゆえに、それは大悪となるのである。もし小善が対象であれば、憎悪、瞋恚の心がいかに激しくとも、それは小悪でしかない。また、もし悪に対する憎悪・瞋恚は、そのためにとる手段・方法は別として、それ自体は善にさえなるのである。
末法御本仏、日蓮大聖人に対し、当時の日本民衆は、幕府権力の中枢から一般民衆にいたるまで、程度の差は万別であったろうが、みな、憎悪と瞋恚の心を抱いたのである。自分たちを救ってくれるべき、主・師・親の三徳を具備した人を憎んだのであるから、それは〝大悪心〟である。「此の悪心の根本は日蓮によりて起れるところなり」の一文に、民衆救済のために起たれた、大聖人の大確信が秘められていることを知らなければならない。
第五章(天変地夭の原因を説く)
本文
守護国界経と申す経あり法華経以後の経なり阿闍世王・仏にまいりて云く我国に大早魃・大風・大水・飢饉・疫病・年年に起る上他国より我が国をせむ、而るに仏の出現し給える国なり・いかんと問いまいらせ候しかば・仏答えて云く善き哉・善き哉・大王能く此の問をなせり、汝には多くの逆罪あり其の中に父を殺し提婆を師として我を害せしむ、この二罪大なる故かかる大難来ることかくのごとく無量なり、其の中に我が滅後に末法に入つて提婆がやうなる僧・国中に充満せば正法の僧一人あるべし、彼の悪僧等・正法の人を流罪・死罪に行いて王の后・乃至万民の女を犯して謗法者の種子の国に充満せば国中に種種の大難をこり後には他国にせめらるべしと・とかれて候、今の世の念仏者かくのごとく候上・真言師等が大慢・提婆達多に百千万億倍すぎて候、真言宗の不思議あらあら申すべし、胎蔵界の八葉の九尊を画にかきて其の上にのぼりて諸仏の御面をふみて灌頂と申す事を行うなり、父母の面をふみ天子の頂をふむがごとくなる者・国中に充満して上下の師となれり、いかでか国ほろびざるべき。
此の事余が一大事の法門なり又又申すべし、さきにすこしかきて候、いたう人におほせあるべからず、びんごとの心ざし一度・二度ならねばいかにとも。
現代語訳
守護国界経という経がある。これは法華経以後に説かれた経であるが、その中に「阿闍世王が釈尊の所へ参上していうには『わが国に大早魃・大風・大水・飢饉・疫病が毎年起る上に、他国よりわが国を攻めている。しかるに、わが国は仏の出現された国である。これはどういうことでしょうか』とたずねた。釈尊が答えていうには『すばらしいことだ。大王よ、よくそのことを質問した。あなたには多くの逆罪がある。その中で、父を殺し、提婆達多を師として私を迫害した。この二罪は重大であるために、このような大難がこのように無量に起こるのである』と答え、更に『わが滅後、末法に入って提婆達多のような僧が国中に充満するとき、正法を持つ僧が一人出現する。彼等悪僧たちが、この正法の僧を流罪・死罪に行なった上、王の后をはじめ、一般庶民の女性までも犯して謗法者の種子が国中に充満するであろう。そしてそのために国中に種々の大難が起こり、やがて他国からも攻められる』」と説かれている。
いま、日本の念仏者は、この経文に説かれているのと同じであり、その上、真言師たちの大慢心は提婆達多よりも百千万億倍もすぎている。その真言宗の奇怪な点についてあらあら述べると、胎蔵界の八葉九尊を絵に画いて、その上にのぼって諸仏の御面を踏んで灌頂という儀式を行なうのである。これは父母の面を踏み天子の頂を踏むような者が国中に充満して、しかも上下万民の師となっているということである。これでどうして国が亡びないことがあろうか。
このことは、私のもっとも大事な法門であるから、またの機会に申しましょう。このことは以前にも少し書きましたが、みだりに人に言ってはいけません。お便りのあるごとに、日蓮に寄せられるお志は、一度二度でなく、何とも感謝のことばもありません。 このことは、私のもっとも大事な法門であるから、またの機会に申しましょう。このことは以前にも少し書きましたが、みだりに人に言ってはいけません。お便りのあるごとに、日蓮に寄せられるお志は、一度二度でなく、何とも…。
語釈
守護国界経
守護国界主陀羅尼経、守護国界主経ともいい、密教部に属するとされる。唐の罽擯国出身の般若三蔵と牟尼室利三蔵訳の共訳があり、十卷十一品よりなっている。
阿闍世王
梵語アジャータシャトゥル(Ajātaśatru)の音写。未生怨と訳される。釈尊在世における中インドのマガダ国の王。父は頻婆沙羅王、母は韋提希夫人。観無量寿仏経疏によると、父王には世継ぎの子がいなかったので、占い師に夫人を占わせたところ、山中に住む仙人が死後に太子となって生まれてくるであろうと予言した。そこで王は早く子供がほしい一念から、仙人の化身した兎を殺した。まもなく夫人が身ごもったので、再び占わせたところ、占い師は「男子が生まれるが、その子は王のとなるであろう」と予言したので、やがて生まれた男の子は未だ生まれないときから怨(うら)みをもっているというので未生怨と名づけられた。王はその子を恐れて夫人とともに高い建物の上から投げ捨てたが、一本の指を折っただけで無事だったので、阿闍世王を別名婆羅留枝ともいう。長じて提婆達多と親交を結び、仏教の外護者であった父王を監禁し獄死させて王位についた。即位後、マガダ国をインド第一の強国にしたが、反面、釈尊に敵対し、酔象を放って殺そうとするなどの悪逆を行った。後、身体中に悪瘡ができ、改悔して仏教に帰依し、寿命を延ばした。仏滅後は第一回の仏典結集の外護の任を果たすなど、仏法のために尽くした。
逆罪
理に逆らう重罪。重禁を犯す罪。
提婆
提婆達多のこと。梵名デーヴァダッタ(Devadatta)の音写。漢訳して天授・天熱という。大智度論巻三によると、斛飯王の子で、阿難の兄、釈尊の従兄弟とされるが異説もある。また仏本行集経巻十三によると釈尊成道後六年に出家して仏弟子となり、十二年間修業した。しかし悪念を起こして退転し、阿闍世太子をそそのかして父の頻婆沙羅王を殺害させた。釈尊に代わって教団を教導しようとしたが許されなかったので、五百余人の比丘を率いて教団を分裂させた。また耆闍崛山上から釈尊を殺害しようと大石を投下し、砕石が飛び散り、釈尊の足指を傷つけた。更に蓮華色比丘尼を殴打して殺すなど、破和合僧・出仏身血・殺阿羅漢の三逆罪を犯した。そのため、大地が破れて生きながら地獄に堕ちたとある。しかし法華経提婆達多品十二では釈尊が過去世に国王であった時、位を捨てて出家し、阿私仙人に仕えることによって法華経を教わったが、その阿私仙人が提婆達多の過去の姿であるとの因縁が説かれ、未来世に天王如来となるとの記別が与えられた。
胎蔵界
真言密教の両部の一つで、金剛頂経に説く金剛界に対し、胎蔵界は大日経に説くもの。胎蔵とは母の胎内に児を蔵するとの意。仏の菩提心が一切を包み育成することを、母胎に譬えたとされる。真言宗では、金剛界、胎蔵界の両部を絵にして、曼陀羅と称している。
八葉の九尊
真言密教で描く胎蔵界曼荼羅は、中央の一院が八葉の蓮華になっていて、そこには大日如来が座し、それを囲む八葉の蓮華の上に宝幢仏、阿弥陀仏、沙羅樹王開敷仏、天鼓雷音仏の四仏、普賢、文殊、弥勒、観音の四菩薩が坐っている。
灌頂
水を頭上にそそいで一定の資格を具備することを証する儀式で、もとはインドで国王の即位する時、および立太子のときに四大海の水を頭上にそそいで祝ったという。真言宗では特にこの灌頂を重んじ、これにより、すみやかに大覚位を証することができると説いている。
講義
守護国界経の文をあげて、まず前半に、大聖人御在世の天変地夭、および他国侵逼の大難に苦しむ日本民衆の不幸の原因がどこにあるかを示されている。後半は、同じくその守護国界経の予言している末法の世相が、まさにその通りに符合していることを明示されている。
また、その一国謗法の中で、特に、真言宗をとりあげ、真言の邪義の一端を、わかりやすい例をあげて述べられている。
つまり、天変地夭や他国侵逼難の原因が逆罪にあるとの、阿闍世王の例を示しての指摘は、天変地夭が大法出現の瑞相であるというこれまでの論議から、もう一歩進めて、核心をズバリ突いておられるわけである。すなわち、慶ぶべきこととしての「天に吉瑞・地に帝釈の動」の天変地夭ではなく、「人の悪心盛んなる」ゆえに起こっている災厄であるから、これを解決するためには、根源にある病因を打ち破り、治癒しなければならない。
それは、同じく守護国界経に示されている「謗法の者が国中に充満し、唯一人の正法の僧を迫害している」ことが、一切の災厄の原因である。したがって、もし、この災いを転じようと思うならば、正法の僧への迫害をやめて、正法の僧に帰依する以外にない。すなわち、日蓮大聖人の教えに髄順することが、天変地夭をおさめ、他国侵逼難という日本民族の命運を決する危機を脱する唯一の方法である、との意である。
ここに、現実に民衆が、社会が直面している苦悩に対して、それを救うのは自分以外にないとの強い確信と、深遠の大慈悲があふれていることを知らなければならない。また、宗教は決して、現実から離れたところで、現実を無視してあるものではないということも、この御文に明らかである。
さらに「釈尊の出現した国が、なぜ幾多の災厄に見舞われるのか」という疑問に対する答えが示しているように、仏法は、これを信受する衆生の姿勢によって、その仏法の偉大な力を湧現して幸福な世界を築くこともできるし、逆に、仏法のない国よりも悲惨な不幸におちいってしまうこともありうるのである。このことは、仏法を受け止める衆生が大事であるという原理を示す文として、非情に重要であろう。
此の事余が一大事の法門なり
本抄に述べられている、大聖人を迫害しているために種々の大災害に苦しんでいるのだということは、大聖人こそ、末法御本仏であるという証拠にほかならない。したがって、これは、大聖人の一大事の法門であり、へたにいえば、増上慢ととられて、大弾圧を招きかねない。身延入山後の大聖人のお考えは、万年尽未来際のために、いかに令法久住するかにあったことが推察される。おそらく、無用の難は、招くべきではないとのお考えから「いたう人におほせあるべからず」と仰せられたのではないだろうか。
また、真言宗の問題については、一貫して慎重を期しておられたようである。これは、真言宗が、天台宗と一体化して、これを論ずる場合は、どうしても天台教義と絡まってくるため、微妙な問題が生じたからであると思われる。また、もう一面は、権力との関係から、真言宗が権力の中枢、特に朝廷と深く結びついていたことが考えられる。
こうした事情から、真言宗の問題については、一貫して慎重を期されたのであろう。このことは、また、折伏、広宣流布の戦いにあたって、単なる蛮勇であってはならない、勇敢であるとともに、そこには細心の注意と賢明な対処がなければならないとの教訓と拝すべきであろう。