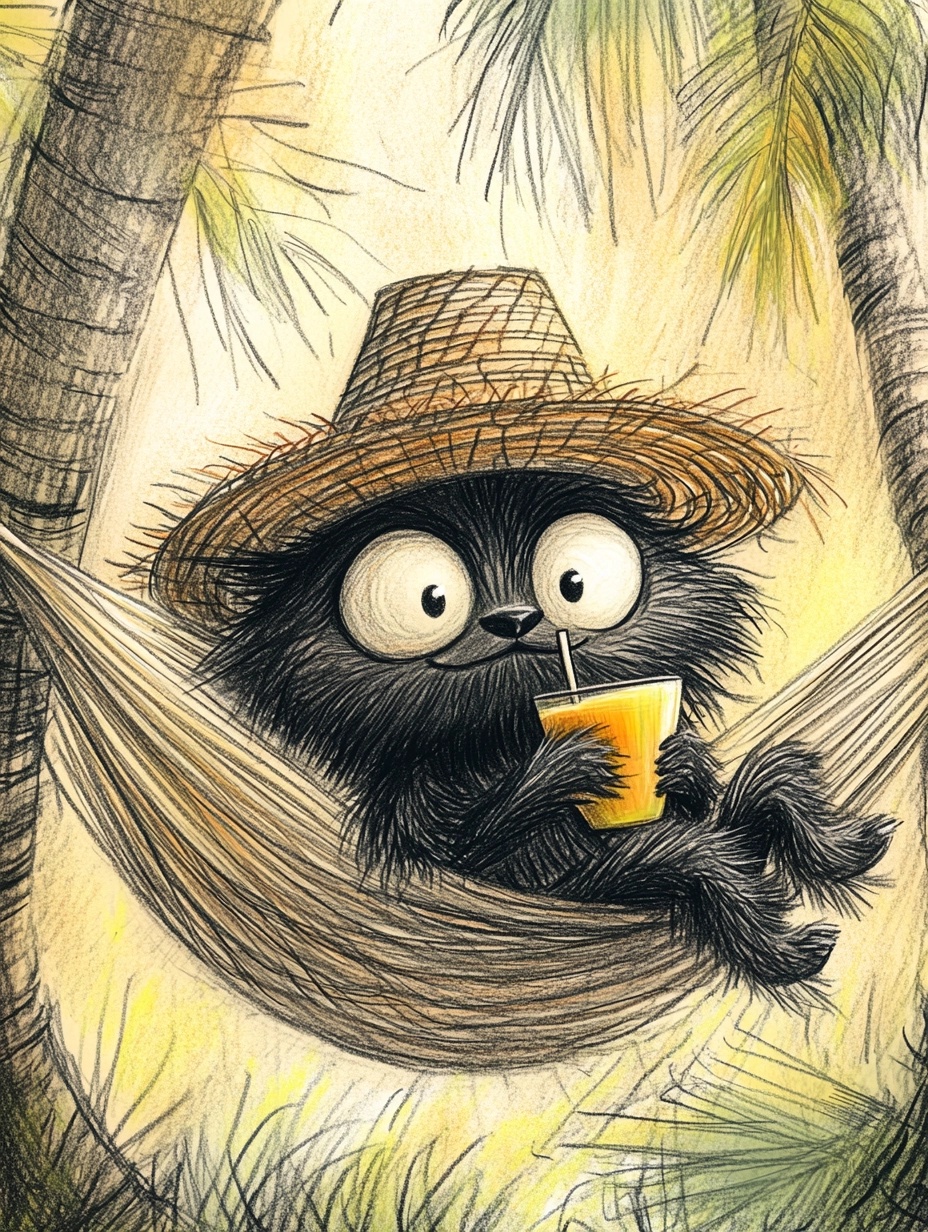わが生命は無限大 いよいよの大信力を
カリフォルニアの空が澄みわたる1990年2月、アメリカの思想家ノーマン・カズンズ氏と語り合いました。
「人間最大の悲劇とは何か、それは、死そのものではない。肉体は生きていても、自分の内面で大切な何かが死んでいく。この“生きながらの死”こそ悲劇なのです」
人々の心に巣食う「無力感」や「シニシズム」の打破を訴えられてきた氏ならではの言葉が今も忘れられません。
「自分の内面の大切な何か」とは、本来、自分自身の生命に具わる偉大な力への確信といえるのではないでしょうか。
氏は、さらに、未来を担う青年に訴えるように語られました。
「人間として生まれてきたからには、だれにも共通した、尊い“使命”があります。それは、人間を信じ、信頼しあうことではないでしょうか。たとえ、どうしようもない悲劇に直面し、煩悶の中に人生の意味を見失ったとしても“人間を信ずる”という、人間本来の在り方は、絶対に忘れてほしくない。
“いのち”という、かけがえのない贈り物、それを、どこまでも肯定し、大切にしていく。他の人の人生を、感情を、絶対に否定しない。無上のものとして認め合っていく。
人間としての最も尊い、その信頼の心だけは放棄してはならない」と。
人間への「尊敬」と「信頼」
日蓮仏法の本質は、人間への「尊敬」と「信頼」であり、生命の無限の可能性と尊厳性への「信」といえます。この強盛なる信仰があるからこそ、「自分が変われば世界が変わる」という人間革命の希望の大道を、朗らかに進むことができるのです。
すべての人が尊極の「仏」の当体であり、自他共の幸福を勝ち開く「力」と「智慧」を具えている。この生命の豊かなる可能性に目を閉ざし、疑い、否定するところに、現代社会を覆う、人々の人間不信や無力感の根源があるのではないでしょうか。 日蓮仏法で「謗法」の教えを責めるのも、それが、人間の可能性を信じ切れない「不信」という根源悪との戦いになるからです。今回は「阿仏房尼御返事」を拝して、人間の尊厳性を信じ抜く実践を学んでいきます。
本文
御文に云く謗法の浅深軽重に於ては罪報如何なりや云云、夫れ法華経の意は一切衆生皆成仏道の御経なり、然りといへども信ずる者は成仏をとぐ謗ずる者は無間大城に堕つ、「若し人信ぜずして斯の経を毀謗せば即ち一切世間の仏種を断ぜん、乃至其の人命終して阿鼻獄に入らん」とは是なり、謗法の者にも浅深・軽重の異あり、法華経を持ち信ずれども誠に色心相応の信者・能持此経の行者はまれなり、此等の人は介爾ばかりの謗法はあれども深重の罪を受くる事はなし、信心はつよく謗法はよはき故なり、大水を以て小火をけすが如し
現代語訳
あなたのお手紙には「謗法の浅い深い、軽い重いに応じて罪報はどのようになるのでしょうか」とある。そもそも法華経の本意は、一切衆生が皆成仏できる道を説いた御経である。そうではあるといっても、この経を信ずる者は成仏を遂げ、謗る者は無間大城に堕ちるのである。法華経譬喩品に「若し人、が信じないでこの経を毀謗すれば、この人は即ち一切世間の仏種を断ずるであろう。乃至その人は命を終えて阿鼻獄に入るであろう」とあるのはこのことである。
謗法の者にも浅深・軽重の異なりがある。法華経を持ち信じていても、誠に色心相応の信者、能持此経の行者はまれである。これらの人々はごくわずかばかりの謗法はあっても深重の罪を受けることはない。信ずる心は強く謗法は弱いゆえである。譬えば大水で小火を消すようなものである。
講義
「万人成仏」が法華経の元意
本抄は建治元年(1275)9月、日蓮大聖人が、身延の地から、佐渡の女性門下・阿仏房尼に送られたお手紙です。
赦免になった大聖人が佐渡を離れてから約1年半、当時、佐渡の門下が抱えていた疑問の一つが「謗法」をどのように捉えるか、ということだったようです。
謗法とは「法に背くという事」です。具体的には「万人成仏」という仏の根本の願いを明かした正法である法華経を謗り、貶め、否定することといえます。
阿仏房夫妻をはじめ佐渡の門下の多くは、長年、念仏を信仰していたようです。念仏は法華経誹謗の教えです。それゆえに、大聖人にお会いして法華経に帰依したといっても、結局、自分は成仏できないのではないか、という不安を覚えていたのかもしれません。
また、当時の習慣からなかなか抜け切れない面や、あるいは、入信まもない人々ばかりで意見の分かれることがあったり、具体的な課題のある人にどう対処すべきか、悩むこともあったりしたのでしょう。謗法の浅い深い、あるいは軽い重いに従って、その罪の報いはどう考えればいいのか。千日尼は、自分だけではなく、佐渡の同志の気持ちを代表してお尋ねしたと思われます。
これに対して大聖人は、まず大前提として、法華経の元意は、「一切衆生が皆、成仏できる道」を説かれたところにあると教えられています。
いかなる人も必ず成仏できるとは、すべての人が仏性という尊極の生命を具え、無限の可能性を有しているということです。さらにかみ砕いていえば、今現在、どんなに苦悩の底にあろうが、その苦境を破って、必ず幸福になる力が、自分自身の生命にあるということです。
この前提を忘れて謗法について論じても、それは単なる観念論になりかねません。
法華経にこそ、万人の成仏が説き明かされている。迷いや疑いの暗雲を払い、この根本の真実を素直に信じることです。そうすれば「成仏をとぐ」ことは間違いない。反対に、この一点を疑い、誹謗するならば「無間大城に堕つ」と仰せなのです。
要するに、自他共の人間の尊厳性を信じ切れるか否か。すべては、この本質から出発しているのです。
妙法は宿業の鉄鎖を断ち切る利剣
如説修行の行者であられる大聖人を、命懸けでお護り申し上げてきた阿仏房夫妻です。御本仏の眼には、この方々こそ「色心相応の信者」「能持此経の行者」と映っていたと拝されます。
大聖人は断言されています。そうした戦う行者には、わずかばかりの謗法があったとしても、深い重い罪を受けることは断じてない、と。「信心はつよく謗法はよはき故」です。
御本尊を信じ抜く根本の一念が、弓の名人がピタリと的を射抜くように、寸毫のぶれもなく定まっているならば、何も恐れることはないのです。
謗法者の充満する悪世末法にあって、悪縁に紛動されることもない。動揺することもありません。「大水」をもって「小火」を消すことができる。
この原理は、私たちも変わりません。
一度、妙法の信心を始めた以上、過去の謗法がどうであれ、いつまでもその業に引きずられることはない。いかなる宿業の鉄鎖をも断ち切る最強の利剣が妙法だからです。
「自分は駄目だ」と、不幸に呻吟しながら自分の人生に絶望してきた多くの庶民がいました。その苦悩の民衆の中に飛び込み、「もう宿命に泣くことはないのだ!」と励まし、共に立ち上がってきたのが創価学会です。
どれほど多くの庶民が、希望と確信を持ち、笑顔を取り戻したことか、それは、まさに自身の無限の可能性を信じられない「無明」の闇を破り、己心の仏界への強靭なる「信」を蘇らせるものです。
厳密にいえば、誰でも信心を始める前は、知らず知らずのうちに、法華経への誹謗や不信の業を積んでいるのかもしれません。そうした呪縛を打ち破り、大空を自在に飛翔するように自由なのです。
本文
涅槃経に云く「若し善比丘法を壊る者を見て置いて呵責し駆遣し挙処せずんば当に知るべし、是の人は仏法中の怨なり、若し能く駆遣し呵責し挙処せば是れ我が弟子真の声聞なり」云云、此の経文にせめられ奉りて日蓮は種種の大難に値うといへども・仏法中怨のいましめを免れんために申すなり。
現代語訳
涅槃経には「若し善比丘がいて、法を壊る者を見て、置いて、呵責し駆遣し挙処しなければ、当に知りなさい。是の人は仏法の中の怨である。若し能く駆遣し呵責し挙処するならば、この人は我が弟子であり真実の声聞である」と。この経文にせめられて、日蓮は種々の大難にあうといっても「仏法の中での怨である」の誡まぬかれるために謗法を責めるのである。
講義
謗法呵責の精神を師子吼
涅槃経の経文です。大聖人は諸御抄に引かれて、謗法呵責の精神を教えられています。
呵責 呵り責めることです。
駈遣 追い払うことです。
挙処 罪を挙げて処断することです。
大聖人は、この経文を身に当てて、「仏法の中の怨」になってはならないと、いかなる大難も覚悟のうえで、謗法の悪と戦い、師子吼されてきたのです。
冒頭からの論旨を踏まえていえば、生命の無限の可能性を閉ざし、人間を無力感に縛り付ける謗法との戦いこそ、折伏精神です。
大聖人は、この御精神のままに、民衆の幸福の実現のために、人々を不孝へ誘う魔性と断固として戦い続けられました。人間の善性を破壊する「悪」に対しては、断固として戦い。その魔性を打ち破っていく。それは、いつの時代にあっても変わってはならない、民衆の宗教の根本精神です。
そのうえで謗法呵責の具体的実践は、教条的であってはならない。本抄では、さらに謗法呵責の姿勢について重要な観点を、千日尼に教えられています。
まず、謗法には「浅深」があり、それに対して謗法を呵責する場合にも、柔軟で多様な対応があることが具体的に示されています。
例えば、真言宗、また密教化した天台宗は、法華経を大日経に劣ると誹謗するから、本来ならば厳しく呵責すべきだが、当時にあたっては、よほどの智者でなければ、大聖人の法門と彼らの法門は見分け難い。そのため、初期の御著作である「立正安国論」で真言・天台の破折をしなかったように、しばらく直接の呵責を指し置くことがある。
謗法が軽罪で責める場合でも、責めないでおく場合がある。自然に謗法を改める人もあれば、相手の謗法を責めて、自分も相手も共に罪を免えてから許す場合もある、等々。
大聖人が教えられる仏法の智慧は決して杓子定規ではありません。そこで大切なのは、謗法呵責といっても、その根本が「慈悲」からの行為なのかどうかです。
「云って罪のまぬがるべきを見ながら聞きながら置いていましめざる事」
道理を尽くして言えば相手も納得でき、罪も免られることを、自らの「眼」と「耳」で分かっているにもかかわらず、そのまま放置して誡めない。それは「眼耳の二徳」を自ら破壊してしまうのであり、他の人に対しては「大無慈悲」になると、厳しく仰せです。
言い換えれば、謗法を呵責するのは、瞋恚や敵対心などではなく、相手を絶対に不幸にさせてなるものかという慈悲からなのです。
続いて「慈無くして詐り親しむは即ち是れ彼が怨なり」「彼が為に悪を除けば即ち是れ彼が親なり」との章安の釈を引かれています。牧口先生以来、創価学会の師弟は、この精神で人々を不幸に陥れる謗法の悪と戦ってきました。
また、それゆえに私たちは、人間を軽賎し、抑圧する日蓮宗の悪を打ち破ってきたのです。
真の謗法厳誡とは、人々を苦しめる魔性を打ち破る実践です。大悪の闇を打ち破るからこそ、大善の光が輝くのです。
どこまでも「人間」を重視
したがって謗法意呵責といっても、かたくなに形式にとらわれたり、机上の論理を当てはめるようなものではない。
17世紀フランスの哲学者パスカルは、内なる魂の在り方を重視する立場から、当時の教会権威が作り上げた「良心例学」事にあてての良心の在り方を、あらかじめ判例として決めておくこと、を厳しく批判されました。“この判例についていえば、善か悪かに思いなやんだり、良心の呵責を受けずに済む”といいう形式主義の偽善を糾弾したのです。この点については、ハーバード大学で第1回の講演でも触れた通り、「人間のための宗教」の大事な規範です。
本抄で大聖人は、わが弟子檀那の中でも、外面の姿だけで信仰の如何を決めつけることはできないとされ、とくに佐渡の一谷入道について言及されています。
一谷入道は、内心では大聖人に帰依しているようでも、周囲に対しては念仏者として振る舞っていました。そのため大聖人は、一谷入道の後生を心配されていたのです。
本抄の直前の5月に一谷入道の妻に送られたお手紙を拝すると、一谷入道に法華経を常に読み聞かせ、妙法へ正しく導くために、あえて家族に譲るという形にして法華経十巻を届けられたことが述べられています。
大聖人は、形式的、外面的に、「これが謗法である」「あの行為が謗法である」などと決めつけ、一方的に断罪するようなことを、なされていません。そうではなく、その人の心根において、法華経の「生命尊厳」「人間尊厳」の精神に違背しているのか、正しく信じているかどうか。この内実が問われなければならなないのです。 奥底の一念は、一見、明らかな姿形としては見えてきません。しかし微妙な一念が生涯にわたる信心を大きく左右するのです。であればこそ、どこまでも純一無垢な信心の根本の一念が大切なのです。それさえ定まっていれば、成仏は疑いないのです。
本文
弥信心をはげみ給うべし、仏法の道理を人に語らむ者をば男女僧尼必ずにくむべし、よしにくまばにくめ法華経・釈迦仏・天台・妙楽・伝教・章安等の金言に身をまかすべし、如説修行の人とは是れなり、法華経に云く「恐畏の世に於て能く須臾も説く」云云、悪世末法の時・三毒強盛の悪人等・集りて候時・正法を暫時も信じ持ちたらん者をば天人供養あるべしと云う経文なり。
現代語訳
いよいよ信心を励んでいきなさい。仏法の道理を人に語ろうとする者を、男女僧尼必ず憎むでろう。憎むから憎むがよい。法華経・釈迦仏・天台・妙楽・伝教・章安等の金言に身を任すべきである。如説修行の人とはこういう人をいうのである。法華経の見宝塔品には云「恐畏の世に於いて、よくわずかの間でも説く」とある。これは悪世末法の時、三毒強盛の悪人達が集まっている時に、正法を暫間でも信じ持つ者を天人が供養するであろうという経文である。
講義
「如説修行」「師弟不二」の人に
「なおいっそう信心に励んでいきなさい」
命懸けで大聖人をお守りした千日尼に対して、それでも「弥」という思いで、弛みなき前進をと呼びかけられています。
私には、広布のため、不惜の闘争を数え切れないほど続けてこられた多宝会、宝寿会、錦宝会の尊き方々が、大聖人から賞讃される千日尼の姿と重なってなりません。
一方で、仏法とは魔との戦いであるがゆえに、信心に油断があってはならないということを教えられていると拝されます。阿仏房・千日尼夫妻らは、大聖人が鎌倉に御帰還された後も、佐渡の地で信心を貫き、勇敢に広布の旗を掲げました。そこに、俗衆増上慢・道門増上慢などの三類の強敵が出現し、門下の人々が理不尽な非難仲傷の礫を浴びたでえあろうことは想像に難くありません。
その悔し涙を全部、大聖人はご存じであられた。「よしにくばばにくめ」くよくよなんかせず、からりと割り切っていきなさいと言われています。牧口先生も、この御文には力強く線を引かれていました。
大聖人御自身が身に当てて読まれた経文には「人間の苦報現世に軽く受くるは斯れ護法の功徳力に由る故なり」(0959:18)とあり、転重軽受は明らかです。まして悪口した人々さえも「毒鼓の縁」で最後は救っていく。広大無辺の大慈悲の仏法です。
何の心配もないのです。何も恐れる必要はないのです。「鉄は炎打てば剣となる」(0958:14)ように、一切の苦難は、自身の生命を金剛不壊に鍛え上げ、宿命の鉄鎖を断ち切って人生を自由に遊戯しゆく力を開発する原動力となるのです。
そのためにこそ、「金言に身をまかす」ことです。この御文にも牧口先生は線を引かれていました。大切なことは、どこまでも経文の通り、御書の通りに信じて生き抜くことです。戸田先生も、御書を拝するたびに、「その通りだ。その通りだ。本当にありがたい」と語られていた。
心から御金言に身をまかせるその人が「如説修行の人」です。ほかならぬ大聖人御自身が、その模範を示してくださいました。その上で大聖人は、師匠と同じく、千日尼もまた「如説修行の人」として生き抜きなさいと教えられているのです。
師弟不二です。師弟共戦です。
見宝塔品の末尾に「恐畏の世に於いて、能く須臾も説かば、一切の天人は、皆な応に供養すべし」とあります。
時をいえば「悪世末法」であり、社会をいえば「三毒強盛の悪人」が充満している世の中において正法を受持し、勇気を奮って人々に語っていく。信心の発露として、たとえ一言一句であっても、自ら進んで人々に語っていく。なんと尊く崇高な菩薩の行動でありましょうか。その人を絶対に諸天善神が護り、供養するというお約束です。
「よしにくばまにくめ」私たちはこの一節を拝し、晴れ渡る青空のように、どこまでも心広々と進むのです。
私は若き日、戸田先生にお会いした直後、詠みました。
希望に燃えて 怒濤に向い/たとい貧しき 身なりとも/人が笑おうが あざけようが/じっとこらえて 今に見ろ
まずは働け 若さの限り/なかには 侮る者もあろう/されどニッコリ 心は燃えて/強く正しく わが途進め
苦難の道を 悠々と/明かるく微笑み 大空仰ぎゃ/見ゆるい未来の 希望峰/ぼくはすすむぞ また今日も
この心に多くの青年たちが続いてくれていることが、私の喜びです。
本文
此の度大願を立て後生を願はせ給へ・少しも謗法不信のとが候はば無間大城疑いなかるべし、譬ば海上を船にのるに船おろそかにあらざれども・あか入りぬれば必ず船中の人人一時に死するなり、なはて堅固なれども蟻の穴あれば必ず終に湛へたる水のたまらざるが如し、謗法不信のあかをとり・信心のなはてを・かたむべきなり、浅き罪ならば我よりゆるして功徳を得さすべし、重きあやまちならば信心をはげまして消滅さすべし、
現代語訳
此の度、大願を立て後生を願っていきなさい。少しでも謗法や不信の失があるならば、無間大城に堕ちることは疑いないであろう。譬えばば海上を船に乗っていくのに、船は粗悪でなくても、水が入ったならば必ず船は沈み、船中の人々は一時に死ぬのである。また、畷は堅固であっても、蟻の穴があけば、必ず最後には湛えた水が溜まらないようなものである。したがって謗法不信の水を抜き取り、信心の畷を固めるべきである。
浅い罪であるならばこちらからゆるして功徳を得させるべきである。重い過失であるならば信心を励ましてその重罪を消滅させるべきである。
講義
「信心のなはて」を強固に
「大願を立てよ」当時の大聖人門下にとっては、何よりも一生成仏の大願でありました。皆が今生における信心を全うして、仏道を成就することを勧められたのです。
しかし、当時に、諸御抄には、大願とは、我が身一人の成仏に限らず、他者をも救っていく法華弘通の願いであることが示されています。「御義口伝」に「大願とは法華弘通なり」(0736:第二成就大願愍衆生故生於悪世広演此経の事:01)と仰せの通りです。
後生善処のために、大聖人は「謗法不信の失」を誡められています。それは無明に覆われた生命の闇にほかならないからです。
この闇を晴らし、己心の中に仏界の太陽を昇らせる根源の力は「信」の一字しかありません。
海上を走る船も、どこかに穴が開いて浸水したら、沈没してしまう。また、次の「なはて」の譬えは、本抄の別名「畷堅固御書」の由来となる一節です。畷、すなわち水田を区切る「あぜ道」が堅固であっても、蟻の穴があれば、そこから田の水が漏れ出て、水が枯渇して、稲も枯れてしまうでしょう。船の穴、あぜ道の穴、この些細な穴から、一見、堅牢な船や田も崩れてしまう。
「不信」という穴も、目には見えません。だから怖い。だからこそ油断禁物です。何があっても一生涯、信心を貫いていくことです。そのために、学会から離れない。師弟の道を外さない。とともに、大切な和合僧の団結を護り抜いていくことです。
「謗法不信のあかをとり・信心のなはてを・かたむべきなり」
進まざるを退転といいます。
ゆえに停滞や惰性を破って「、月月・日日につより給へ・すこしもたゆむ心あらば魔たよりをうべし」(1190:11)との御文の通り、今日より明日へと、前進し続けていくことです。
仏法とは、生命の無限の可能性を閉ざす、根本の迷いである「無明」との間断なき戦いです。この内なる戦いを忘れた時、「冥きより冥きに入る」(0560:06)が如く、苦悩の闇に堕してしまう。
私たちが謗法不信を誡める本質は、まさに、ここにあるのです。
本文
尼御前の御身として謗法の罪の浅深軽重の義をとはせ給う事・まことに・ありがたき女人にておはすなり、竜女にあにをとるべきや、「我大乗の教を闡いて苦の衆生を度脱せん」とは是なり、「其の義趣を問うは是れ則ち難しと為す」と云つて法華経の義理を問う人は・かたしと説かれて候、相構えて相構えて力あらん程は謗法をばせめさせ給うべし、日蓮が義を助け給う事・不思議に覚え候ぞ不思議に覚え候ぞ、
現代語訳
尼御前のお立場で謗法の罪の浅深、軽重の意味を問われた事は、実に希有な女性であられる。竜女にどうして劣るであろうか。法華経提婆品に「我れ大乗の教を闡いて苦の衆生を度せん」と説かれているのはこのことである。また「その義趣を問うことは、是れ則ち難しいことである」といって、法華経の義理を問う人はなれがたいと説かれている。心して力あるかぎりは、謗法を責めていきなさい。日蓮が義を助けられることは、実に不思議に感じられてなりません、不思議に感じられてなりません。
講義
一人の「求道」が創価の前進に
最後に、千日尼が、「謗法の罪の浅深軽重の意義」を質問したことを、あらためて賞讃されて「女人成仏」の道を開いた竜女に劣らないであろうと言われています。
引用の提婆品の教文からは、千日尼が単に個人的な関心から質問したというよりも、佐渡の同志が正しい信心を全うしてほしいという願いからであったと窺われます。
そして、「同志の皆の心に引っかかっていた問題を取り上げて、よくぞ聞いてくださいましたね」との、師匠の深い信頼と賞讃のお心が伝わってくるようです。
思えば、わが恩師・戸田先生は、よく質問会を行ってくださいました。
「いい質問です」「大事な質問をしてくれて、うれしい」と讃えられました。
幹部には、折々に「何でも、聞きに来なさい」と指導された。真剣な質問に対してはどんなにお忙しい時でも、先生はうれしそうに、丁寧に答えてくださった。
問えば必ず前進が始まります。疑問が晴れれば、そこにはみずみずしい確信が生まれます。心からの納得は、喜びと自信を生みます。私たち創価の和合僧は、これからも求道と納得の対話で意気揚々と進むのです。
汝自身の生命を信じよ
本抄の結びに「相構えて相構えて力あらん程は謗法をばせめさせ給うべし、日蓮が義を助け給う事・不思議に覚え候ぞ不思議に覚え候ぞ」と仰せです。
“共に戦ってくれて、ありがとう”と、弟子に対する慈愛のこもる表現です。
師が弟子と共に、謗法の社会の闇を正義の光明を照らしていく、これほどの歓喜はありません。これはどの不思議はありません。
「御義口伝」の有名な一節に、
「始めて我心本来の仏なりと知るを即ち大歓喜と名く所謂南無妙法蓮華経は歓喜の中の大歓喜なり」(0788-03)とあります。
謗法不信の闇を払い、自身の生命の真実を知った瞬間、胸中には赫々たる希望の太陽が昇るのです。それこそ「歓喜の中の大歓喜」でありましょう。
人間の内なる生命こそが最大の宝です。
にもかかわらず、人々は自分の外にばかり宝を探している。なぜか?人間を信じる力が弱くなっているからです。自分自身を信じられないからです。その結果が現代の混迷なのではないでしょうか。
汝自身の生命を信じよ!そこに最大の力が具わっているのです。
『論語』に、印象深い師弟の対話が記されています。
一人の弟子が、師である孔子の教える道を学ぶことをうれしく思いながらも「自分には力がたりないのです」と口にした。
確かに、力が足りなければ、進めるだけ進んで中途で終わることがあるかもしれない。しかし、一番の問題はそこではない。
孔子は声を強めて弟子に言った。
「今お前は自分から見きりをつけている」
「今女は画れり」。やってみないで、どうして自分は駄目だと諦めてしまうのか、それではいけない、と。
戸田先生は、「青年は自分を信じよ」と呼びかけられました。誰でも自分の生命に無限の可能性がある。すべてに勝ゆく。絶対勝利の妙法の当体は、わが生命に他ならない。なればこそ、創価の青年は、強盛の大信力を奮い起こして、わが生命に具わる仏の無限の力、師子王の力を取り出して、断固として楽しく愉快に生き抜いてもらいたい。
55年前(1958)の2月、私は戸田先生から遺言の如く「300万世帯」の拡大の目標を託されました。そして私と共に立ち上がらんとする若き力の脈動を感じ、恩師の口癖であった「後生畏るべし」との言葉を、日記に書き留めました。
今、私は再び「後生畏るべし」と、頼もしき青年部の諸君の大躍進を見つめています。
若き君たちよ、貴女たちよ、青年の大いなる「熱」と「力」を発揮し、我が生命の本源の光を放ちながら、我が使命の舞台で、自由自在に、幸福勝利へ乱舞してくれたまえ。